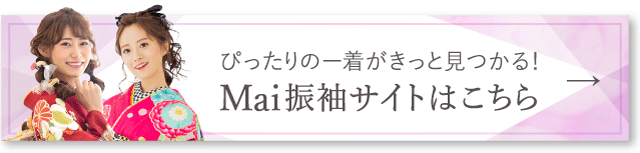着物姿、美しく着こなしたいけれど、半衿と重ね衿の違いってよく分かりませんよね。
特に初めて着物を着る方や、何度か着たことがあるけれどまだ自信がない方にとって、衿周りのアイテム選びは悩みの種かもしれません。
この二つのアイテムは、見た目は似ていますが、役割や選び方が全く違います。
この記事では、半衿と重ね衿の違いを分かりやすくご紹介します。
着物姿の格上げに役立つ情報が満載ですので、ぜひ最後までお読みください。

半衿と重ね衿の違いとは
半衿の役割と種類
半衿は、長襦袢の衿元に縫い付ける、肌着のような役割を持つアイテムです。
着物の衿元を汚したり、汗などが吸着するのを防ぎ、着物の衿元を美しく保つために欠かせません。
種類としては、無地のシンプルなものから、刺繍やレースがあしらわれた華やかなものまで、さまざまなデザインがあります。
重ね衿の役割と種類
重ね衿は、半衿の上に重ねる装飾品です。
別名「伊達衿」とも呼ばれ、着物を何枚も重ね着しているような、豪華な見た目を演出します。
重ね衿を使うことで、衿元に華やかさをプラスし、着物の印象を大きく変えることができます。
種類も豊富で、単色のシンプルなものから、複数の色が組み合わされたもの、レースやパール、つまみ細工などの装飾が施されたものまで、さまざまなデザインがあります。
半衿と重ね衿の素材比較
半衿は肌に触れるため、肌触りの良い綿や絹などが多く使われます。
一方、重ね衿は装飾品としての役割が強いため、より華やかな素材や、耐久性のある素材が使われる傾向があります。
絹やポリエステル、そして近年では、さまざまな素材の組み合わせが見られます。
半衿と重ね衿の着け方比較
半衿は長襦袢に縫い付けます。
一方、重ね衿は、着物の衿元と長襦袢の半衿の間に挟み込んで着付けます。
着付けの際には、重ね衿の位置やバランスに気を配り、美しく着こなすことが重要です。
半衿と重ね衿の選び方ポイント
着物との色の合わせ方
半衿は、長襦袢の色や着物全体のトーンと調和するように選びます。
一般的には、長襦袢の色と近い色を選ぶことが多いです。
重ね衿は、着物全体のコーディネートのアクセントとして、着物地の色や柄と相性の良い色を選ぶのがポイントです。
着物に入っている色や、反対色を選ぶことで、全体のバランスを整え、より華やかな印象にすることができます。
ただし、着物と全く同じ色は、重ね衿の存在感が薄くなってしまうため、避けた方が良いでしょう。
柄やデザインの選び方
半衿は、着物全体の柄や色と喧嘩しないように、シンプルな無地のものや、控えめな柄のものを選ぶのが無難です。
重ね衿は、着物全体のコーディネートのアクセントになるため、柄やデザインも自由に選ぶことができます。
個性を出すなら、レースやパール、つまみ細工などの装飾が施されたものもおすすめです。
TPOに合わせた選び方
半衿は、普段着からフォーマルな着物まで幅広く使えますが、重ね衿は、フォーマルな場面でより効果を発揮します。
結婚式や入学式などのお祝いの場では、華やかなデザインや素材のものを選び、普段着の場合は、シンプルなものを選ぶと良いでしょう。
まとめ
半衿と重ね衿は、どちらも着物の衿元を美しく見せる重要なアイテムですが、役割や選び方が異なります。
半衿は肌着のような役割で、汚れや汗の浸入を防ぎます。
一方、重ね衿は装飾品で、華やかさをプラスします。
素材やデザイン、季節感、TPOなどを考慮して、それぞれのアイテムを適切に選ぶことで、より美しく、着こなしの幅を広げることができるでしょう。