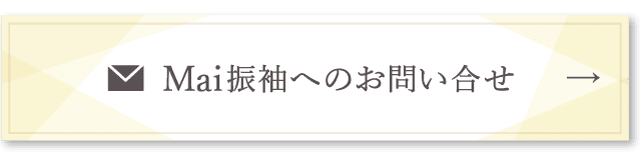二十歳を迎え、新たな人生の節目を迎える。
「成人式」という儀式は、一体いつから始まったのでしょうか?現代の華やかな成人式は、長い歴史と社会情勢の変化によって形作られてきました。
そこで、この記事では古来の儀式から現代の姿に至るまで、その変遷をご紹介します。
成人式というイベントを通して、社会と個人の繋がり、そして未来への展望をどのように捉えてきたのか、その歴史を紐解いていきます。
現代の成人式いつから始まったのか
古代の成人儀礼元服と裳着
奈良時代以降、男子は数え年で12~16歳になると「元服」という儀式を行いました。
これは単なる通過儀礼ではなく、社会人としての第一歩を踏み出す重要な節目でした。
髪型を大人のスタイルに整え、服装も大人用のものへと変更。
幼名から改名し、冠をかぶるなど、外見だけでなく、社会的な役割の変化を象徴する儀式でした。
貴族社会では複雑な手順で行われていた元服ですが、江戸時代になると庶民の間では簡略化され、前髪を切り落とす程度になったようです。
女子の場合は「裳着(もぎ)」という儀式があり、腰から下にまとう裳を身につけることで大人の女性としての象徴となりました。
これもまた、結婚の時期と重なることが多く、髪を結い上げる「髪上げ」と同時に行われることもありました。
元服、裳着ともに、年齢は地域や身分によって異なり、必ずしも一律ではありませんでした。
戦後の社会情勢と成人式の制定
現代のような、地域の新成人が一堂に会して祝う成人式が始まったのは戦後です。
1946年、現在の埼玉県蕨市で「青年祭」が開催されたことが、その発祥と言われています。
この青年祭が全国に広がり、1949年1月15日が「成人の日」として制定されました。
1月15日という日付は、元服の儀を新年最初の満月に執り行う風習に由来するといわれています。
しかし、これは旧暦に基づいたものであり、新暦では必ずしも1月15日が満月とは限りません。
ハッピーマンデー制度の影響
2000年の祝日法改正(ハッピーマンデー制度)により、「成人の日」は1月の第2月曜日に変更されました。
当初は1月15日だったものが、なぜ第3月曜日ではなく第2月曜日に変更されたのでしょうか?それは、1月17日が「防災とボランティアの日」であることに関係しています。
もし1月1日が土曜日だった場合、第3月曜日は1月17日となり、二つの祝日が重なってしまいます。
これを避けるため、第2月曜日に設定されたのです。
成人式の変遷と社会との関わり
高度経済成長期と成人式
高度経済成長期、成人式は社会的な一大イベントとして隆盛を極めました。
経済発展に伴い、人々の生活水準が向上し、華やかな成人式は、若者たちの未来への希望と、社会からの祝福を象徴する場となりました。
盛大な祝賀会や、晴れ着姿での記念写真撮影などが一般化し、社会全体で祝福ムードが高まりました。
バブル経済崩壊後の変化
バブル経済崩壊後は、社会全体の空気が変化し、成人式に対する価値観も多様化しました。
派手な祝賀会よりも、個人の成長や未来への展望を重視する風潮が強まりました。
参加率の低下や、式典内容の簡素化なども見られるようになりました。
現代社会における成人式の意義
現代社会において、成人式は依然として重要な意味を持っています。
しかし、その意義は、単なる祝賀会という枠を超え、個人の自立や社会参加への意識を高める場として捉えられるようになっています。
地域社会との繋がりを再確認したり、新たな社会の一員としての自覚を促す役割を担っていると言えるでしょう。
参加率の低下や、式典への批判的な意見も存在する一方で、個々の市町村がさまざまな工夫を凝らし、出席率向上に努めています。
例えば、人気の観光地や、参加しやすい時期・季節を選んで開催するなど、それぞれの地域の特性を活かした工夫が見られます。

まとめ
日本の成人式は、古代の「元服」や「裳着」といった成人儀礼から始まり、戦後の社会情勢の変化の中で現代の形へと発展しました。
高度経済成長期には華やかな祝祭として盛況を極めましたが、バブル経済崩壊後には、その意義やあり方が問われるようになりました。
現代では、個人の自立や社会参加への意識を高める場として、その役割が再認識されています。
ハッピーマンデー制度による日付変更や、地方自治体によるさまざまな工夫も、現代の成人式を理解する上で重要な要素です。
成人式は、単なる儀式ではなく、時代を反映し、社会と個人の関わりを象徴する、歴史と文化が凝縮された大切な日なのです。