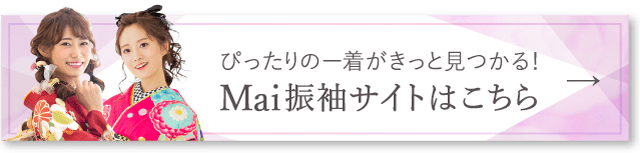着物姿、美しいけれど…着崩れが心配?
せっかくの着物姿、着崩れで台無し…なんて経験はありませんか? 美しい着姿を保つには、着付けや歩き方、そして万が一の着崩れへの対処法を知ることが大切です。
今回は、着物の着崩れを防ぐための着付けと歩き方、そして着崩れ時の具体的な直し方をご紹介します。
着物をより安心して、そしてもっと自由に楽しんでいただくための情報を提供します。

着崩れを防ぐための着付けと歩き方
着崩れの原因を理解する
着崩れの大きな原因は大きく分けて3つあります。
1つ目は、動きが大きいことです。
着物は身体に沿って着るため、大きな動きをすると布地がずれ、帯がほどけやすくなります。
2つ目は、補正が甘いことです。
洋服の下着とは異なり、着物は平面的に作られています。
身体の凹凸をそのままにすると、着物と体の間に隙間ができ、着崩れしやすくなります。
3つ目は、着付けが緩いことです。
腰紐は着物を支える重要な役割を果たします。
緩めると着物がずれ、着崩れにつながります。
着付けのポイントとは?着崩れ防止のための基礎知識
着崩れを防ぐためには、着付けの際にいくつかのポイントに注意しましょう。
まず、滑りにくい素材の腰紐を使用することが重要です。
綿やモスリン素材、あるいはゴムバンドなどもおすすめです。
また、体型補正をしっかり行うことも大切です。
フェイスタオルや補正下着などを活用して、身体の凹凸をできるだけなくすようにしましょう。
着付けの手順としては、まず肌襦袢、長襦袢を着てから着物、帯と順に整えていきます。
腰紐を締める際は、胃の上ではなく腰骨の上で、息を吸ってから締めることで、苦しさを感じにくく、着崩れも防ぎやすくなります。
帯を締める際も、帯全体ではなく下の方を締めるようにすると、より安定します。
上前と下前の裾の角を上げることで、裾が広がりにくくなります。
美しい所作で着崩れを防ぐ歩き方
着物の着崩れを防ぐためには、歩き方にも注意が必要です。
大股で歩くと裾がめくれやすいため、内股気味に、小さな歩幅で歩くようにしましょう。
また、歩く際には着物の裾を軽く押さえるようにすると、着崩れを防ぎ、所作も美しく見えます。
腕を高く上げたり、腰をひねって振り返ったりする動作は着崩れしやすいので避け、身体全体を使って動くように心がけましょう。
着崩れした時の応急処置と具体的な直し方
衿元がゆるんだ時の直し方
衿元がゆるんだ場合は、身八つ口に手を入れて衿を引っ張り、ゆるんだ部分を帯の下に入れ込みましょう。
それでも衿が浮いている場合は、おはしょりの衿先を下に引き、余った部分を中にたくし込んで整えます。
衣紋が詰まって衿が緩んだ場合は、背中の真ん中を下に引っ張り、もう一度衣紋を抜いてみましょう。
帯が下がってきた時の直し方
帯が下がってきたら、一度帯をぐっと持ち上げて元の位置に戻します。
胴回りの帯がゆるんでいる場合は、背中側の帯の下に小さなタオルやハンカチを差し込むと解消できます。
帯揚げも緩んでいる可能性があるので、一緒にチェックしましょう。
帯揚げが出てきた時の直し方
帯揚げが出てきたら、片手で帯を浮かせて、帯揚げを帯と着物の間に差し込みます。
外れてしまった場合は、前の部分をほどいて、もう一度帯と着物の間に差し込んで結び直しましょう。
上前の裾が下がってきた時の直し方
上前の裾が下がってきたら、おはしょりの下に手を入れ、下がった裾を腰紐に挟み込み、おはしょりを整えます。
階段などで裾を踏んでしまった時にも、この方法を試してみてください。
お尻周りがたぶついた時の直し方
お尻周りがたぶついた場合は、たぶついた部分を両手でなで上げ、たるんだ分をおはしょりの下の腰紐に挟み込みましょう。
座ったり立ったりする動作でたぶつきやすいので、こまめにチェックしましょう。
その他の着崩れと対処法
その他、背中や腰にゆるみが生じた場合は、背中側のおはしょりを下に軽く引っ張ると解消できます。
おはしょりが大きく出すぎてしまった場合は、出すぎている部分を帯の下に入れ込み、縫い目を合わせ、シワにならないように丁寧に整えましょう。
男性の場合、帯が上にあがってしまうと、両手で帯をつかみ、ぐっと下に引き下げることで修正できます。

まとめ
着物の着崩れを防ぐためには、着付けと歩き方に注意することが大切です。
滑りにくい腰紐を使用し、体型補正をしっかり行い、内股気味に小さな歩幅で歩くことで着崩れを予防できます。
万が一着崩れが生じた場合でも、この記事で紹介した応急処置を参考に、落ち着いて対処すれば、美しい着物姿を保つことができます。
これらのポイントを意識し、着崩れの心配なく、着物を楽しんでください。